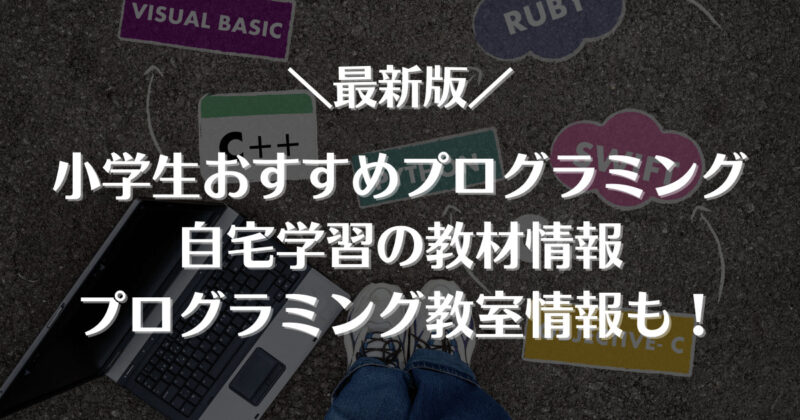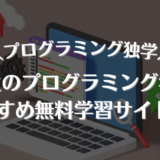「小学生の子どもに、プログラミング学習を始めさせたい」と考える親御さんは多くいらっしゃるでしょう。Webで無料のプログラミング教材をたくさん見かけるけれど、小学生が自宅でも学べるのか気になりますよね。
そこで今回は、プログラミング学習を小学生から開始するメリットや、自宅学習でプログラミング学習に取り組む際の、ポイントや教材をご紹介します。
是非、お子さんがプログラミングを始めるときの参考にしてください。
小学校低学年でプログラミング学習を開始するメリット
プログラミング学習を始めるなら、小学校低学年からがおすすめです。
子どもは成長過程で、9歳ごろから自分自身を客観的に見れるようになります。その際、個人差はありますが、自己に対して劣等感を持ちやすくなります。
劣等感は、ときに「苦手意識」を生みます。プログラミング学習でつまづいたときに、苦手なものとして認識され、記憶に残ります。
しかし、好奇心旺盛な低学年のうちからプログラミング学習をスタートさせれば、楽しみながら能力を身につけられます。
プログラミング学習をおすすめする具体的な理由として
- 論理的思考が身につく
- 問題解決能力が身につく
- コンピュータのスキルが得られること
- 小学校ではプログラミング学習が必修化になったこと
などが挙げられます。それぞれ以下で解説します。
論理的思考が身につく
プログラミング習で「論理的思考」が身につきます。そして「プログラミング的思考」ができるようになるのです。
- 「論理的思考」とは・・・目的を達成するためには、どういった手順でどのようにしたら達成可能か、筋道を立てて手段を考えなければなりません。このように物事を考えることを論理的思考といいます。
- 「プログラミング的思考」とは・・・論理的思考の一つです。前述の論理的思考に基づき筋道を立てて考えた上で、さらに効率を重視して最適な手順を考えることをいいます。思いついた色々な手段のなかで最適なものはどれなのか、さらに考えを深めていきます。
次に挙げる「問題解決能力」もプログラミング的思考が必要です。
問題解決能力が身につく
プログラミングを学習し、論理的思考が身につくと、「問題解決能力」も習得できます。問題解決能力とは「自分で問題点を発見すること」そして、「解決策を論理的に考えること」も習得できます。子どもがこの能力を身につけるメリットは以下の2点です。
- 自分からすすんで学習するようになる
- 自分でじっくり物事を考えるようになる
1.自分からすすんで学習するようになる
プログラミング学習を通して、論理的思考と問題解決能力を身につけた子どもは、学校の勉強も受身ではなく、率先して学ぶ姿勢を取れるようになります。授業中も自発的に発言し、コミュニケーション能力が向上しますよ。
これが習慣化すると、他の勉強も楽しくなり、学習意欲の向上につながるでしょう。
2.自分でじっくり物事を考えるようになる
論理的思考と問題解決能力のある子どもは難しい問題に直面したときこそ力を発揮します。
今の状況を少しでも良くするためにはどうしたらいいか、まずは自分で考えて周りとディスカッションしたり、コミュニケーションをとったりすれば、協調性も身につきますよ。
コンピュータのスキルが得られる
プログラミング学習はパソコンやタブレットを使うため、コンピュータの操作や知識、スキルを得られます。
遊びを交えながらプログラミングを取り入れ、楽しみながらプログラミングを身につけられるでしょう。だんだんとパソコン操作にも慣れ、IT関連の知識やスキルを子どものうちから身につけられるでしょう。
子どもに興味をもってもらうために、子ども向けのプログラミング教材は遊びながらゲーム感覚で学べるものが多いですよ。色々試してみるのがおすすめです。
これからの生活で、コンピュータはどんどん重要な役割を果たすようになります。プログラミング学習は幅広く活用できる知識が身に付くのもメリットのひとつです。
小学校ではプログラミング学習が必修化になった
プログラミング学習は2020年より小学校の授業で必修となりました。
文部科学省の「小学校プログラミング教育の手引」にプログラミング教育のねらいが以下のように明記されています。
①「プログラミング的思考」を育むこと
②プログラムの働きやよさ、情報社会がコンピュータ等の情報技術によって支えられていることなどに気付くことができるようにするとともに、コンピュータ等を上手に活用して身近な問題を解決したり、よりよい社会を築いたりしようとする態度を育むこと
③各教科等の内容を指導する中で実施する場合には、各教科等での学びをより確実なものとすること
現代でコンピュータは、身の回りの生活になくてはならない存在となりました。そのため、コンピュータをうまく扱える人材が多く必要とされる世の中なのです。小学校のプログラミング学習の投入によって、子どもたちの未来に可能性が広がるでしょう。
小学生にプログラミング教室と自宅学習どっちがいいの?
では実際に、子どもにプログラミングを学ばせようと考えたとき、自宅学習とプログラミング教室に通うのは、どちらがいいのか迷う親御さんも少なくないでしょう。
そこで、プログラミング教室のメリットとデメリットをそれぞれ解説します。
プログラミング教室のメリット
プログラミング教室で学ぶメリットはたくさんあります。
- カリキュラムがきちんと組まれているので効率よく学べる
- 講師にすぐ質問ができるので挫折しにくい
- 同じ年頃の仲間と一緒に学べる
- 将来の選択肢が広がる
それぞれ説明します。
1.カリキュラムがきちんと組まれているので効率よく学べる
プログラミング教室では、ゲームやロボットなど子どもの興味を引くカリキュラムが組まれています。子どもたちを飽きさせない工夫と、効率よく学べる工夫もされているので、自宅学習よりも早く理解ができる可能性が高いです。
2.講師にすぐ質問ができるので挫折しにくい
いつも側に講師がいるため、わからないことがあったらすぐに質問ができます。講師からヒントを得て自分で問題解決したら、次のステップに進めます。
自分自身で進歩を実感できれば、やる気につながりますね。
3.同じ年頃の仲間と一緒に学べる
同じ年頃の子どももいるので、仲間同士でコミュニケーションをとりながら学べます。一緒に学ぶ仲間がいるとモチベーションも保ちやすいですね。
4.将来の選択肢が広がる
プログラミング教室では、プログラミングだけでなく、基本的なコンピュータ操作についても学べます。身につけた知識や技術は、IT関連の仕事だけでなく、色々な業界でも活かせます。
タイピングやプログラミング的思考はどんな場面でもきっと役に立つでしょう。将来の選択肢が広がりますね。
プログラミング教室のデメリット
プログラミング教室で学ぶデメリットは以下のようなものがあります。
- 費用がかかる
- 送り迎えの手間がかかる
- パソコンなどの機器の使用時間が長くなる
1.費用がかかる
プログラミング教室に通うには、当然ですが受講料などの費用がかかります。
パソコン操作やプログラミングは短期間で取得できるものではないので、長期間通い続けることを視野に入れておかなければなりません。
また、帰宅後の復習は、自宅のインターネット環境やパソコンなどを整える必要もあるため、コストがかかります。
2.送り迎えの手間がかかる
また、プログラミング教室に限らず、子どもの習い事に送り迎えはつきものです。送迎に保護者が時間を取られるのは、避けて通れません。
3.パソコンなどの機器の使用時間が長くなる
プログラミングが面白くなって熱中し始めると、子どもは家でもやりたくなります。そのため、パソコンやタブレットを長時間にわたって使用するでしょう。
パソコン機器の長時間使用で、視力が低下する可能性も高くなるのです。また、外で遊ぶ時間が減ると、運動や自然と触れ合う機会も減ります。偏った学習になれば、他の教科の学力低下を招くおそれもあるので注意しましょう。
プログラミング教室を楽しんで続けるためにも、親子できちんと話し合ってルールを決めるといいですよ。
小学生が自宅でプログラミングを学習するポイント
小学生が自宅でプログラミングを学習するには、子ども本人の学習意欲がないと成り立ちません。子どもの学習意欲を高めるために、親御さんの協力が大きな役割を果たします。
自宅でプログラミングを学習する5つのポイント
- 具体的な目標を作る
- なるべく手や口を出さずに見守る
- 子ども自身で考え発見させる
- 挫折しそうになったら一緒に考える
- 失敗を恐れない
以下で解説します。
1.具体的な目標を作る
プログラミング学習を確実に進めるには、目標設定が必要です。ただ教材を使って闇雲に勉強を進めても、効果的な学習はできません。モチベーションを維持できずに、結果的に挫折につながってしまう恐れもあります。
まずはお子さんの今のレベルを確認しましょう。レベルがわかったところで、今より少しだけ高いところに目標設定します。たとえば、まだ1つしかプログラムを組めないとしたら、「一週間で3つの動作をプログラムできるようになる」などにすると子どもも挫折せずに取り組めますよ。
それをクリアしたら次の目標を設定します。目標設定は親御さんだけで決めてしまうのではなく、お子さんと話し合って決めるといいですよ。
こうして小さな目標をいくつも確実にクリアしていくと子どもの心は達成感で満たされます。次のステップに向けてモチベーションを維持するためにも細かな目標作りには有効です。慣れてきたら、一週間単位だけでなく一年後にはこうなりたい、など長期目標を設定してみるのもおすすめですよ。
2.なるべく手を出さずに見守る
お子さんのプログラミング学習をできるだけ見守りましょう。「どうやってプログラムしたらいいのかわからない」「思い通りの動きにならない」など困って手が止まる場面を頻繁に見るかもしれません。
この時に大事なのは、親御さんがすぐに教えたり、操作しないことです。子どもが自分で解決策を探す様子をしばらく見て待ちましょう。それから必要であれば、答えそのものでなく、答えを導き出すためのヒントを教えましょう。
口も手も出さずに見守るのは簡単なようで難しいです。しかし、子どもが自分で壁を超えると新たな成長につながります。ぐっとこらえて見守る事を心掛けましょう。
3.子ども自身で考え発見させる
プログラミング以外のことでも、子どもが自分自身で考えて発見する体験は大切です。
たとえば、ロボット型プログラミング教材を使用したときに、ロボットに付属しているセンサーやボタンや音声装置の機能や使い方を知る必要があります。
親御さんが教えてしまうのではなく、子どもが自分で動かし、調べて考えながら発見できるといいでしょう。子どもが自分で調べてわかった経験がプログラミングへの理解につながります。
子ども自身が行った経験の繰り返し積み重ねで、自信が生まれ、どんどん新しいことにチャレンジしていく意欲が生まれます。
4.挫折しそうになったら一緒に考える
プログラミング学習に限らず、途中で挫折しそうになるのは珍しくありません。
どんなに頑張って考えても、わからないことが何度も続くと先に進まなくなり、挫折につながってしまいます。
そんなときは親御さんが、お子さんと一緒に考えましょう。何をしたかったのか、どこでつまずいたのか、作業を最初から順番に言葉にして説明させてみます。そうすることで、考えを整理でき、解決策につながる手段がわかってくるかもしれません。
5.失敗を恐れない
プログラミング学習するうえで、エラーは必ずあります。プログラミングしたものが、思い通りに動かないときは、当然どこかが間違っているということです。これを修正するために別の方法を考え、試していきます。
大切なのは、学習が順調にいかなくても失敗を恐れないことです。たくさんの失敗や試行錯誤を経験することは、今後の人生で数々の問題に直面したときにも役立ちますよ。
ただ、失敗は大きく成長するために必要ですが、ストレスを感じるときもあります。周りの大人は放っておかずに、ちゃんとフォローして声掛けをしてあげることを、忘れないでくださいね。
プログラミングを自宅で学習するときの教材選びのコツ
プログラミングを自宅で学習するときの教材はどんなものがあるでしょうか。どんな基準で選べばいいのか、選び方のコツを解説します。
- 対象年齢から選ぶ
- 料金で選ぶ
- アプリの対応機種で選ぶ
- 学習方法で選ぶ
- 実際の口コミやインストール数で選ぶ
1.対象年齢から選ぶ
どんなプログラミング教材にするべきか迷ったら、子どもの年齢を基準にしてみましょう。
年齢と理解度を考え、本人にあった内容を選ぶと挫折しにくくなります。初めのうちはとくに、子どもに合ったレベルの教材からスタートして、できるようになったら少しずつ難易度をあげて進めましょう。子どもが自分でクリアできて、プログラミング=楽しいものと思えると学習が長続きします。
長く続けたら、子ども自身のレベルが上がってきています。この時、子どものレベルに合わせて、難易度を上げていかないと途中で飽きてしまうので注意が必要です。
プログラミング教材それぞれに対象年齢が設定されているので、参考にしてください。
2.料金で選ぶ
プログラミング教材にいくらお金をかけるかも選ぶ基準です。
小学生向けのプログラミング教材の料金は無料〜数万円まで幅広く、内容も難易度もさまざまです。小学校低学年で初めてプログラミングを学ぶのであれば、無料のものか低価格のものを試すことをおすすめします。
一つだけでなく複数の教材を試し、好みや向き不向き、レベルをはかってみましょう。後ほど無料で楽しめるプログラミング教材を紹介します。
やりたいことが決まっていたり本格的に学ぶつもりなら、最初から有料の教材を選んでもいいでしょう。
3.アプリの対応機種で選ぶ
使ってみたいプログラミング教材が、スマホやタブレット、パソコンなどのデバイスにちゃんと対応しているかどうか確認しましょう。
アプリストアで対応機種かどうか記載があるはずですが、ダウンロードするときになかなか進まなかったり、エラー表示がでるのであれば、残念ながらそのデバイスには対応していない可能性もあります。
4.学習方法で選ぶ
プログラミング教材には大きく分けて「ソフト型教材」と「ロボット型教材」があります。
ソフト型教材は、主に画面上のキャラクターにプログラミングで指示を出して動かすものです。ゲームやアニメが作れるものもあるので、この分野に興味がある子どもは興味を持ちやすいでしょう。
ロボット教材は、ロボットなど実際に工作したものにプログラミングで指示を出して動かすものです。工作やものづくりの分野に興味があるなら、こちらがおすすめですよ。
どちらの教材も、小学生には、JavaScriptなどのプログラミング言語ではなく、指示を書いたブロック「ビジュアルプログラミング言語」を組み合わせてプログラムする教材を選ぶのがいいでしょう。
5.実際の口コミやインストール数で選ぶ
プログラミング教材のアプリを検索する際に、インストール数や口コミを読んでみて選ぶのも方法の一つです。
人気のアプリは、インストール数が多く、口コミも高評価(高得点)になります。逆に人気のないものはインストール数も少なく、口コミも低評価(低得点)ですよね。
無料で楽しめる自宅で学べるプログラミング教材5選
ではここで、無料で楽しめて自宅で学べるプログラミング教材5選を紹介します。色々試してみて、お子さんに合う教材を見つけてくださいね。
- スクラッチ(Scratch)
- スプリンギン(Springin)
- ビスケット(Viscuit)
- アワーオブコード(Hour of Code)
- プロゲート(Progate)
1.スクラッチ(Scratch)

スクラッチは世界的に人気のあるサイトです。ビジュアルプログラミング言語でプログラミングを学びます。
使い方と特徴
- 指示を表す文字が書かれたブロック(ビジュアルプログラミング言語)を組み合わせ、プログラミングする。
- ブロックを組み合わせて、自分で設定したキャラクターにプログラミングして動かす。
アニメやゲームに発展させることもできます。
公式サイト
2.スプリンギン(Springin)

スプリンギンもビジュアルプログラミング言語でプログラミングする無料のアプリです。スマホやタブレットにアプリをダウンロードして使用します。
使い方と特徴
- 指示を絵に表したアイコン(ビジュアルプログラミング言語)を組み合わせて、自分で描いた絵にプログラミングして動かす。文字がないため、未就学児でも操作できる。
- 作った作品をアプリ内にあるマーケットで、アプリ内だけで使えるコインで売買もできる。このコインは課金するものではなく、アプリ起動時のボーナスと自分の作品が売れたときに入手できるしくみ。
自分の作品が売れる方法も考えるので、ビジネス感覚も学べますよ。
公式サイト
3.ビスケット(Viscuit)

ビスケットビジュアルプログラミング言語でプログラミングするアプリです。
使い方と特徴
- 「メガネ」と呼ばれるビスケット独自のツール(ビジュアルプログラミング言語)に、自分で描いた絵を当てはめて動きを作っていく。文字ではないため、未就学児でも操作できる。
- 学習が進めばアニメやゲームなどが作れる。
学校向けのページも用意されています。
公式サイト
4.アワーオブコード(Hour of Code)
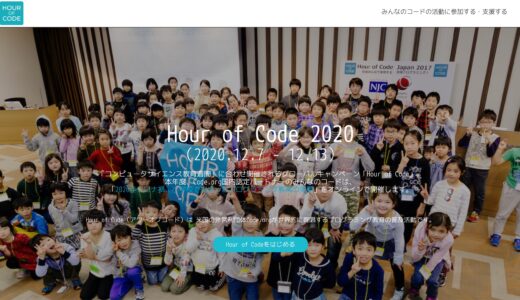
世界一億人以上が学んでいるコンピューターサイエンスのサイトです。幅広い年代で楽しまれています。なんと60種類以上もの教材があります。
教材の内容
- スクラッチのような指示を表す文字が書かれたブロック(ビジュアルプログラミング言語)を組み合わせてプログラミングする教材
- JavaScriptなどの本格的なプログラミング言語を使ってコードを書いて学ぶ教材
「スターウォーズ」や「アナと雪の女王」などのキャラクターが登場するものもありますよ。
公式サイト
5.プロゲート(Progate)

プロゲートは本格的にプログラミングをやってみたい人におすすめのサイトです。無料版と有料版があり、無料版では18レッスン受講可能です。
内容は・・・
- HTMLやCSS、JavaScriptやRuby、Pthonなどのプログラミング言語を使用してコードを書く。
- スライドの解説を見ながら実践して学べる。
無料版をやり終えて、さらに学習したいときは、有料版に登録してみましょう。
公式サイト
まとめ
小学校低学年の子どもにプログラミング学習をおすすめする理由と、自宅学習でプログラミング学習に取り組む際の、ポイントや教材の選び方をご紹介しました。
ご紹介した内容を参考にして、ぜひ無料の学習サイトやアプリで自宅学習を始めてみてください。親子で一緒に学んで、プログラミングの面白さを楽しみましょう。